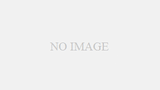焼肉屋、お好み焼き屋、居酒屋、スナック等の色んな飲食店を税務調査しました。
現金商売なので無予告調査が多いが、、
現金商売ですので無予告調査が多いですが、現金商売だからといって無予告調査が許されるかと言ったらそうではありません。
国税通則法第74条の10に事前通知を要しない、無予告調査が許される場合が規定されています。
その運用ルールには、「単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえない」とはっきり記載されています。
(国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について(法令解釈通達)5-7)
その後の5-9で例示されているように、「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」のあることが必要です。
これを知らない調査官もいるので、しっかりと主張したいところです。
自家消費(家事消費)の漏れに注意
この間、プライベートである飲食店に入ってカウンターで一人飲んでいました。
カウンターだったので店長らしき人と仲良くなって話をしていました。
当たり前のように自分のお店の飲み物を飲んでいたので税金大丈夫?って聴いたら、自分のお金(借入)で飲んでるから大丈夫だよと言ってました。
どうみても売上に計上しているようには見えません。
単に個人借入で飲み物を仕入れているということを言っているのだと思います。
自家消費(家事消費)として売上を計上することとは違いますよと突っ込みたくなりました。
所得税では売価の70%を売上として計上することになります(仕入金額の方が大きければ仕入金額)。
もし、売上として計上していない場合には、売価で計上することになります。
(所得税基本通達39-1、39-2)
仕訳としては以下の通りです。
事業主貸 ●●/ 売上(家事消費等) ●●
決算書の月別売上金額の最後に「家事消費等」が載っています。
また、消費税でも課税標準に含めて消費税を納める必要があります。
課税標準に含める金額は売価の50%となります(仕入金額の方が大きければ仕入金額)。
(消費税法基本通達10-1-18)
法人ですとその人に対する現物給与となり、消費税が仕入控除できなくなり、源泉所得税がかかってきます。
内観調査は基本的に行っている
調査官は飲食店の税務調査の前には実際にお客さんとして行っています。
内観調査と呼ばれます。
何を見ているかというと、正直、皆さんが思われるような大したことはしていません。
レジの有無のチェックと入店時にどういうお客さんがいて出入りをメモしていました。
外のゴミ袋から割りばしを数えて客数と売上を検討するなんてことは当然していません。
ドラマの世界です。
当事前に上司には内観調査することを伝えて、終了後には連絡します。
内観調査の翌日には、必ず、書類等を作成して上司に報告しています。
飲食店の間取り図については作成していました。
ただ、内観調査をしたからといって、必ずしも税務調査をするわけでもありません。
そして、内観費は予算計上されているので、消化することを考え年度末である3月間際にすることが多かったです。