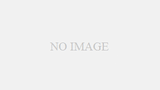税務通信No.3856(令和7年6月23日)を読んでいて、気になる判決内容が掲載されていました。
不動産管理会社のサブリースによる賃貸料が争われた裁判で、高等裁判所で国が逆転勝訴しました。
現在、最高裁に上告しているので、引き続き注目の裁判です。
事案の概要
Aさんは不動産賃貸業を営むともに、不動産管理会社であるX社の代表取締役でした。
Aさんは自己所有の複数の不動産をX社に一括して賃貸して、X社は入居者に転貸していました。
税務署は、AさんがX社に一括で賃貸した契約が、所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるとして、いわゆる「同族会社の行為計算否認規定」を適用して更正しましたが、地裁は、当たらないと判断しました。
税務署は、AさんがX社以外の不動産管理会社と行った契約と、AさんがX社に一括で賃貸した契約に一部重複している不動産があり、AさんがX社に一括で賃貸した契約は形式を整えたに過ぎない点を高裁で新たに主張しました。
高裁は、一転して地裁の判断を取り消しました。
理由は以下の「実態との乖離」と「賃貸料が著しく低い」という2点です。
実態との乖離(理由①)
X社が2~4人の従業員で、数百人の入居者に対応することは困難であるとした上で、重複している不動産以外についても、同じようなことが行われているのを推認するのが合理的であると指摘しました。
個人が不動産管理会社に管理を委託しており、その後、資産管理会社を設立して、サブリースを行うという展開は多いです。
実質的には、AさんがX社以外の不動産管理会社に賃貸して、入居者からの賃貸料の支払口座をX社名義にしており、X社は窓口業務をしていたに過ぎないとしました。
賃貸料が著しく低い(理由②)
X社がAさんから一括で賃貸した賃貸料に占める入居者から受け取っていた賃貸料の割合が、54.7~59.8%と、一般的な料率は80~90%であり、Aさんにメリットがないため、想定しがたいと言っています。
AさんがX社に一括で賃貸した賃貸料は以下に基づき設定されていました。
・Aさんが負担する必要資金を下回らない金額にすること
・X社の事業運営と経費がまかなえること
・売却予定物件の賃貸料収入を除外しても、X社の事業運営に支障が生じないようにすること
X社の信用を高め、X社の資産を増やす目的があるとして、AさんがX社の株主であり、代表取締役であるからこそできる行為、計算(同族会社の行為計算)に他ならないとしました。
サブリースの一般的な料率は80~90%であり、それを下回ると否認されるリスクがあるということです。